相続財産に借金があった場合の手続きと判断の流れ
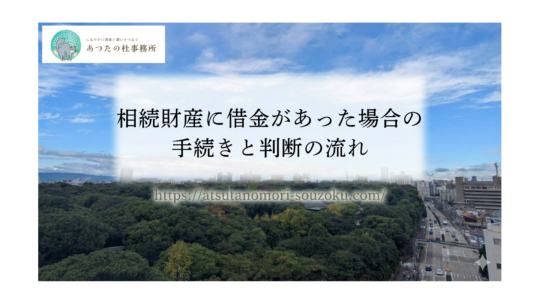
はじめに|
「親に借金があったらどうすればいいの?」
「相続したら借金まで背負うのでは?」
そうした不安を抱く方は少なくありません。
実は、相続とはプラスの財産(預金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も対象になります(民法896条)。しかし、適切な手続きを取ることで、不必要な債務を回避できる仕組みもあります。
この記事では、司法書士の実務経験をもとに、借金のある相続の基本と対応の選択肢をわかりやすく解説します。
1. 相続人は借金も相続する
被相続人が亡くなった時点での借金は、法定相続人が法定割合に応じて相続します。また、被相続人が誰かの保証人であった場合、その「保証債務」も原則として相続対象となります(民法896条)。
2. 相続放棄とは?(民法939条)
借金を含め、相続財産を一切引き継がない手続きが「相続放棄」です。
家庭裁判所に申述することで、最初から相続人でなかったものとみなされます。
注意点:
申述期限は「自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内」(民法915条1項)
放棄後は、不動産・預金も含めすべての財産を取得できなくなります。
財産を処分した場合(例:預金を引き出す、車を売るなど)は放棄が認められず、「単純承認」と扱われる可能性があります(民法921条)。
3. 限定承認とは?(民法922条)
「相続財産の範囲内で借金を返済する」制度が限定承認です。
相続人全員の同意が必要で手続きも複雑です。
実務上の注意点:
限定承認は一般的に利用者が少なく、専門家の関与が必須になることもあります。
財産調査を正確に行わないと、想定外の債務が出てくる可能性も。
4. 3か月の熟慮期間でやるべきこと
借金の有無が不明な場合でも、3か月以内に判断を下さなければ、単純承認(すべてを引き継ぐ)とみなされます。
この期間に行うべき調査:
・通帳やカード履歴の確認
・信用情報機関への開示請求(CIC、JICCなど)
・保証人情報の確認(過去の契約書や知人の証言)
5. 借金を相続した場合の対応フロー
相続することを選択した場合は、以下のような流れで進めます。
・債権者への連絡・確認
・相続人間で返済割合や分担の協議
・必要に応じて債務整理や分割返済の交渉
・財産の売却や分配計画の立案
6. よくあるトラブルと注意点
相続放棄をしたつもりでも、財産の一部を処分した事実があると、法定単純承認とみなされ、放棄が無効になる恐れがあります。
また、放棄や限定承認をした場合、次順位の相続人(兄弟や甥・姪など)に負債のリスクが回ることもあるため、家族間での情報共有も大切です。
7. 専門家に相談すべきケース
以下のような場合は、早めに司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。
・借金の有無が不明な場合
・相続人が複数おり、協議が難しい場合
・保証人の地位に関するトラブルがある場合
・限定承認を選択したいが、手続きが煩雑な場合
まとめ
相続財産に借金が含まれているかどうかは、相続開始後すぐに確認すべき重要事項です。
対応を誤ると、不要な債務を負うことになりかねません。相続放棄や限定承認といった制度を理解し、3か月以内に正しく判断することが重要です。
名古屋市熱田区のあつたの杜事務所では、相続放棄や限定承認を含む相続の無料相談を承っています。
悩んだら、まずは一度ご相談ください。
💡相続・資産承継のご相談は「あつたの杜事務所」へ
不動産と相続に強い司法書士が、ご家族の想いに寄り添いながら、最適な解決策をご提案します。
「何から始めればいいか分からない…」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
📅 ご予約方法(24時間受付)
- 🌐 WEB予約フォーム:こちらをクリック
- 💬 LINEで相談予約:LINE公式アカウントはこちら
- ☎️ お電話でのお問い合わせ:052-977-5960(受付時間:9:00〜18:00/土日祝も対応)
🔹あつたの杜事務所(司法書士)
〒456-0031 名古屋市熱田区神宮四丁目6番25号 ナガツビル2B
相続・遺言・家族信託・不動産承継の専門家として、
「しなやかに。資産と想いをつなぐ。」をテーマにサポートしています。
